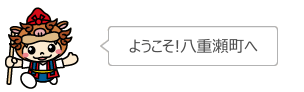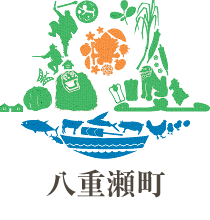公開日 2021年02月01日
■行政区/34
■人口・世帯数/令和6年6月30日現在
■参 考 資 料 /具志頭村勢要覧・東風平町勢要覧・沖縄県営繕の歩み2005、2017
■下表の行政区をクリックすると紹介文へ移動します。
東風平地区 13の字と9つの自治会の計22行政区
| 東風平 | 伊 覇 | 上田原 |
| 屋宜原 | 富 盛 | 世名城 |
| 高 良 | 志多伯 | 当 銘 |
| 小 城 | 宜 次 | 外 間 |
| 友 寄 | 友寄第一団地 | 白川ハイツ |
| 大倉ハイツ | 屋宜原団地 | 県営外間団地 |
| 友寄東ハイツ | 外間高層住宅 | 県営伊覇団地 |
| 県営屋宜原団地 | ||
具志頭地区 10の字と2つの自治会の計12行政区
| 具志頭 | 新 城 | 後 原 | 大 頓 |
| 玻名城 | 安 里 | 与 座 | 仲 座 |
| 港 川 | 長 毛 | ||
| 県営長毛団 | 県営大頓団地 | ||
東風平(Kochinda) 人口:6,639 世帯数:2,587

政治、経済の中心地として小・中学校、郵便局など公共施設が集中しています。沖縄の自由民権運動の父、謝花昇の出身地として知られ、東風平運動公園内には銅像が建立され、後世も遺徳が讃えられています。旧暦七夕には綱引き、豊年祭には獅子舞、棒術が行われます。
伊覇(Iha) 人口:3,190 世帯数:1,145
国道507号に接して集落が形成され、幹線道路沿いに各種店舗が進出し、商店街が拡大しています。個人経営のアパートが多く、昭和49年には字民出資の伊覇共同住宅が建てられ話題を呼びました。
 上田原(Uetabaru) 人口:620 世帯数:218
上田原(Uetabaru) 人口:620 世帯数:218

昭和7年に字東風平の字志道原一帯を区域として行政分離。サトウキビと畜産を営む農家が多く、住宅は耕地の中に散在しています。また火返し池などの拝所もあります。
 屋宜原(Yagibaru) 人口:2,098 世帯数:749
屋宜原(Yagibaru) 人口:2,098 世帯数:749

町の北東に位置し、南城市に隣接。北端を饒波川が流れ、平坦な耕地が広がっています。昭和23年に字東風平から行政分離。3番目に分離したため“三男村”とも呼ばれていました。
 富盛(Tomori) 人口:1,774 世帯数:691
富盛(Tomori) 人口:1,774 世帯数:691

小高い丘の勢理城には、県内で最大最古の石彫大獅子があり、町名の由来でもある八重瀬岳を望むように蹲居し、去る大戦の猛烈な戦火にもびくともしなかったと伝えられています。御嶽も多く神事、伝統行事も数多く残されています。豊年祭で行われる唐人行列・大和人行列は有名です。
 世名城(Yonagusuku) 人口:1,249 世帯数:500
世名城(Yonagusuku) 人口:1,249 世帯数:500

南側を八重瀬岳、与座岳にいだかれた緑豊かな静かな字です。ハルヤー(屋取)が3つに点在し、集落が形成されているのが特徴です。一戸当たりの耕地面積は広く、昔から農業で栄えてきました。豊年祭には棒術やウスデークが行われます。
 高良(Takara) 人口:268 世帯数:122
高良(Takara) 人口:268 世帯数:122

糸満市字与座に隣接。中心部にある児童館を核に、字ぐるみの活性化運動を展開しています。その昔、髙良はゴルフ場へ抜ける道路途中の小高い地に集落を形成していましたが、今から160年前に現在地へと移動したと伝えられています。旧暦七夕には綱引き、旧暦8月15日には豊年祭が行われます。
 志多伯(Shitahaku) 人口:936 世帯数:387
志多伯(Shitahaku) 人口:936 世帯数:387

糸満市豊原と隣接。地域芸能が盛んで、字民総出の道ズネーや伝統の獅子舞、棒術、舞台芸能が地域の文化力が高く、字のシンボルである獅子加那志を祝う豊年祭が年忌ごとに開催されています。
 当銘(Toume) 人口:623 世帯数:311
当銘(Toume) 人口:623 世帯数:311

糸満市字座波と隣接。北側の豊見城城趾を背に南斜面に住宅が広がる純農村地域です。旧暦7月15日には門中をエイサー支度で回る“ニンブチャー”や字小城と共同の龕甲行事が行われます。
 小城(Kogusuku) 人口:729 世帯数:284
小城(Kogusuku) 人口:729 世帯数:284

糸満市字北波平と隣接。東側から眺めると集落は小高い丘を切り開いたような所にあり、坂道が多いのが特徴。その昔、豊見城真切から東風平真切に編入されました。サトウキビ作のほか畜産も盛んで、隣接する当銘との共同龕甲行事や、“聖地”の森にある「ニーセー石」が有名です。
 宜次(Gishi) 人口:909 世帯数:385
宜次(Gishi) 人口:909 世帯数:385

戦前までは「宜寿次(ぎすじ)」と呼ばれていたましたが、戦後「寿」の一字が消え、現在の宜次となりました。字に伝わる正月のクエンナは、沖縄の20日正月の原型といわれる独特な行事とされている。
 外間(Hokama) 人口:432 世帯数:208
外間(Hokama) 人口:432 世帯数:208

南風原町と豊見城市と隣接。盆地状で耕地面積が狭く、商売や勤め人が多いのが特徴。旧盆には子どもたちによる獅子舞やエイサーが行われます。
 友寄(Tomoyose) 人口:1335 世帯数:577
友寄(Tomoyose) 人口:1335 世帯数:577

中央部を饒波川が流れ、字内には南部商業高校や島尻養護学校、酪農研修センターがあり、字のシンボルである獅子舞をモデルにした県内最大級の巨大獅子舞滑り台があります。旧暦8月15日の獅子舞は有名です。
 友寄第一団地(Tomoyose Daiichi Danchi) 人口:238 世帯数:96
友寄第一団地(Tomoyose Daiichi Danchi) 人口:238 世帯数:96

南部商業高校に隣接、町初の振興住宅として49年の入居以来、意欲的な自治会活動を展開し、平成6年には、自治会誕生20周年式典が盛大に行われた。
 白川ハイツ(Shirakawa Haitsu) 人口:343 世帯数:162
白川ハイツ(Shirakawa Haitsu) 人口:343 世帯数:162

国道507号から少し入った小高い丘の上にあり、見晴らしのよい閑静な新興住宅地で子ども会、自治会、婦人会の活動が活発。昭和61年には10周年記念式典が催され、これまで「第二団地」の名称で親しまれてきたが、一戸建てということで、自治会名変更の動きがあり、平成10年4月1日から「白川ハイツ」でスタート。
 大倉ハイツ(Okura Haitsu) 人口:253 世帯数:114
大倉ハイツ(Okura Haitsu) 人口:253 世帯数:114

国道507号沿いに形成された振興住宅地。昭和51年の発足以来、那覇に近い地理的条件に恵まれ各種商店の立地が多く将来が有望視されています。
 屋宜原団地(Yagibaru Danchi) 人口:481 世帯数:221
屋宜原団地(Yagibaru Danchi) 人口:481 世帯数:221
団地誕生後すぐに自治会を結成し、結束力が固く町内行事に積極的に参加しています。青年会活動も活発で新興住宅地に文化の息吹を吹き込もうと青年エイサーを結成、各イベントにも積極的に参加しています。
 県営外間団地(Kenei Hokama Danchi) 人口:201 世帯数:82
県営外間団地(Kenei Hokama Danchi) 人口:201 世帯数:82
友寄第一団地と白川ハイツと隣接し、昭和62年8月より入居が始まり、小高い丘の上にあり大変環境が良く活気に溢れています。
 友寄東ハイツ(Tomoyose Higashi Haitsu) 人口:411 世帯数:163
友寄東ハイツ(Tomoyose Higashi Haitsu) 人口:411 世帯数:163

南風原町字神里と隣接。住宅公社による分譲住宅として、平成7年に入居が始まり、閑静な住宅地として今後の発展が期待されています。
 外間高層住宅(Hokama Koso Jutaku) 人口:288 世帯数:122
外間高層住宅(Hokama Koso Jutaku) 人口:288 世帯数:122

町の北部に位置し、最も那覇に近い団地。那覇糸満線の開通で利便性の優れた住宅として今後の発展が期待されています。
 県営屋宜原団地(Kenei Yagibaru Danchi) 人口:175 世帯数:60
県営屋宜原団地(Kenei Yagibaru Danchi) 人口:175 世帯数:60
平成17年度に完成。建物配置が扇形で、住戸のプライバシー及び日照・通風の確保が図られた造りで、南側に設けられた広場は建物の圧迫感を和らげるとともに、地域住民の交流など多様な利用が可能な空間となっています。
 県営伊覇団地(Kenei Yagibaru Danchi) 人口:167 世帯数:46
県営伊覇団地(Kenei Yagibaru Danchi) 人口:167 世帯数:46
平成29年に完成。南側の擁壁や住棟の大きな壁面が与える圧迫感を和らげるため広い敷地を活かした並木道を形成。。集会所は別棟となっており、スクールバス送迎用の回転広場を設けています。
 具志頭(Gushichan) 人口:1,836 世帯数:881
具志頭(Gushichan) 人口:1,836 世帯数:881

昔は具志上と書かれグシカミと呼ばれていました。明治12年の廃藩置県の頃までには、グシカミはグシチャンと呼ばれるようになりました。字内には、観光拠点施設「南の駅やえせ」や郵便局、社会体育館、改善センターなど多くの公共施設が所在し、青年会による伝統芸能エイサーが、旧盆に行われます。
 新城(Aragusuku) 人口:1,476 世帯数:563
新城(Aragusuku) 人口:1,476 世帯数:563

新城は、東風平間切から具志頭間切に編入されました。旧盆に披露される青年会によるエイサーや、集落内の祝い事などの場で踊られているシーヤーマーの伝統芸能があります。
 後原(Koshihara) 人口:1,454 世帯数:578
後原(Koshihara) 人口:1,454 世帯数:578

明治41年に、新城村から分離して字後原を新設。当時は、行政上の一自治区としての設定で、本籍や住所は字新城のままでした。昭和61年6月1日に、大字新城の区域を変更して、大字後原が誕生しました。
 大頓(Oton) 人口:289 世帯数:120
大頓(Oton) 人口:289 世帯数:120

字大屯の前身は、旧士族の人々が首里から現在の部落の地に移住してつくった大屯原屋取。昭和6年に字玻名城より分離して字大屯を新設しましたが、本籍や住所は玻名城のままでした。平成元年に大字具志頭、大字玻名城の区域を変更して、大字大頓が誕生しました。
 玻名城(Hanagusuku) 人口:833 世帯数351
玻名城(Hanagusuku) 人口:833 世帯数351

玻名城は昔、花城と書かれていました。花城村は、グスク時代には多々名按司の居城多々名城の城下村で、当時の間切の中心であり、多くのおもろにもうたわれているように、名高く富み栄えた村でした。玻名城には、旧暦8月15日には獅子舞と棒術が催されます。
安里(Asato) 人口:918 世帯数:385

安里の集落は、古くは現在の具志頭社会体育館の付近にありました。安里村住民の一部が、地味肥沃で耕地の広い現在の安里に座嘉武村をつくり、一部のものは現在のサザンリンクスの入口付近に移って喜納村をつくりました。やがて、琉球王府の農村施策により、各村は現在の安里の地に移り、安里村を建設しました。安里には、旧盆にエイサー、旧暦7月17日にウフデーク、旧暦8月15日には綱引きと棒術が行われます。
与座(Yoza) 人口:198 世帯数:85

与座は、昔は上と呼ばれ、現在の字与座南方の山の上に現存する与座の殿付近にありました。親村である仲座村の東の方に新設された村だったので、上と呼ばれました。上村は、仲座と合併した時もありましたが、やがて与座村に改められました。
仲座(Nakaza) 人口:498 世帯数:235

仲座は、昔は中座と書かれ、現在の仲座の南方山の上にある上城城趾の南西方にあり、上城城主と血縁の人々の居住していた村でした。やがて仲座に改められ、戦後昭和21年には与座と仲座が合併して「字富座」がつくられましたが、しばらくして、字与座、字仲座に分かれました。
港川(Minatogawa) 人口:799 世帯数:403

糸満からの移住者によってつくられた集落で、町唯一の港町。港川の前身は、上港川。上港川は、糸満からの移住者も年々増加し、特に冬場の良い漁場をひかえ漁業も発達し、明治36年に港川村として新設されました。旧暦5月4日に行われるハーレーと角力大会は有名です。
長毛(Nagamou) 人口:942 世帯数:397

昭和2年に字港川より分離して字長毛が新設され、さらに昭和40年に大字長毛が誕生しました。戦前の長毛は粟石採掘と関連して沖縄各地から人々が集まり、一時期は人口が2千人を越え、本島南部では糸満、与那原に次ぐ大都会でした。
大頓団地(Oton Danchi) 人口:160 世帯数:74

県営大頓団地は、平成3年7月1日から入居が始まりました。中層構造になっており、3棟建ての2DK30部屋、3DK50部屋になります。
長毛団地(Nagamou Danchi) 人口:169 世帯数:76

県営長毛団地は、平成3年7月1日から入居が始まりました。中層構造になっており、4棟建ての2DK32部屋、3DK56部屋になります。